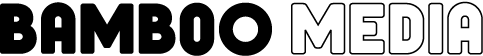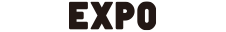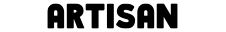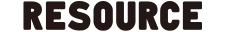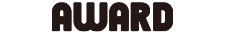2024年、東京・世田谷区にある百貨店「玉川高島屋S.C.」が開業55周年を迎えるにあたり、本館の2階フロアをリニューアルした計画の中で、利用者が行き交う共用空間の一画に、植栽と木、そして個性的な形状のベンチが据えられたシーティングスペースが設けられた。この空間は、二子玉川周辺の自然から着想を得た有機的な要素が取り込まれ、川原の小石をイメージした形状のテラゾーベンチと、その表面に浮かび上がる様々な素材の表情が印象的だ。このテラゾーには、大理石の端材や、九谷焼の陶磁器片が用いられている。同空間の設計を手掛けた永山祐子建築設計の永山祐子氏、横田英雄氏、そして、ベンチの素材において協働した関ヶ原石材の久川翼氏、CACLの奥山純一氏に、プロジェクトがスタートした経緯と、アップサイクルな視点での素材づかいについて話を伺い、speciaL Interviewとしてお届けする。
取材・文/BAMBOO MEDIA ポートレート撮影/千葉正人

—–今回のプロジェクトがスタートした経緯について教えて下さい。
永山氏:
以前に関ヶ原石材さんの会社へお伺いした際、たまたま端材置き場を見る機会があり、大きなサイズで使うと良い値段の大理石が小さな塊で積まれていました。その端材のほとんどが廃棄されてしまうということを聞いて、どれも素敵な表情の石なのにもったいないと思い、ぜひストックして何か別の用途を見いだせないかと相談したのが始まりでした。同じ時期に、ガラスや銅線のチップ、タイルの破片など様々な素材をテラゾーに用いる実験的なプロジェクトを進めていて、関ヶ原石材さんで出会った多様な石が、それとマッチする予感がしていました。この取り組みは、エシカルな観点からも可能性があるものですが、私個人としては、様々な素材の新しい一面を見られる面白さのほうが先にありました。そこから、同社に端材となった石をコツコツと貯めておいてもらいました。

建材の端材に宿る素材としての魅力について語る永山祐子氏

「玉川高島屋S.C. 本館」2階のシーティングスペースに設けられたテラゾー製のベンチ(撮影/阿野太一)
久川氏:
数多くの建築空間づくりに携わらせていただく中で、そこに用いる大理石はできるだけ余すことなく使いたいと工夫はしているものの、最終的に出る端材は細かく粉砕して、建築や土木現場の再生土などに用いるくらいしか行き場がなく、自然物ではありますが、エシカルなサイクルをつくりにくい建材という課題があります。ただ、端材であっても「宝石のようだ」と魅力を感じていただける声はあり、私たちも何とか活かすことができないか模索をしてきました。永山さんからお話をいただいた時は、デザインの力によって石の魅力がもう一度輝き出すように思えてワクワクしました。

関ヶ原石材の久川翼氏

関ヶ原石材の倉庫で眠っていた端材の中から特徴的なものを集めていった(画像提供/永山祐子建築設計)
永山氏:
陶器片の調達で協力いただいたCACLの奥山さんとは、ミラノ・サローネで出会い、そこで同社が行っている九谷焼の陶磁器片の再利用のプロジェクトの話を聞いたのが始まりでした。当初は、陶磁器片を活かした金継ぎやアート的な使い方を模索されていましたが、一つひとつは美しいけれど、再利用を進めていくためにはスケールが小さいことが課題かもしれないという話をしました。例えば、イタリアの石畳のような建築素材として使えたらいいかもというアイデアを出しながら、テラゾーにも使えるか実験を始めました。
奥山氏:
私たちCACLは、⽯川県能美市を拠点として、規格外品や廃棄物となってしまう工芸品、陶器のかけらを集め、アート作品や他の場所で使えるマテリアルとして再利用し、新たな価値を生み出すことを目指しています。2024年の能登半島地震の直後からは、震災によって出てしまった九谷焼を始めとする陶磁器片を中心に、金継ぎや輪島塗といった様々な手法とかけ合わせ、新たなオブジェクトとして生まれ変わらせる取り組みを続けています。
ただ、永山さんの言う通り、この取り組みを広めるためには、建材のようなもっと大きな市場に関わる再利用の方法を見つける必要があり、今回のプロジェクトには大きな可能性を感じています。

CACLの奥山純一氏
—–テラゾーベンチはどのようなプロセスでつくられていったのでしょうか。
永山氏:
テラゾーベンチの施工をしてもらった原田左官工業所さんに、石や陶磁器片を持ち込んで、テラゾー仕上げが可能か実験を繰り返しました。まず、石はテラゾーの仕上げとして磨いていくと、ものによっては元の石の表情よりもとてもポップな色合いが表れたりして、多様な石の個性を感じることができるようになり、それが並ぶテラゾーは「石の標本」のような楽しい存在感を見せてくれました。私の中では、関ケ原石材さんの倉庫に行った時の、世界中の石に囲まれた空間の楽しさが思い出されました。

骨材となった石の色、陶器片の形状により様々な表情を楽しめる。右の画像は原田左官工業所による制作風景(画像提供/永山祐子建築設計)
久川氏:
今回は15種類以上の石が使われていて、レイアウトを決める前に、青や赤、黄色、ピンクなどある程度の色合いで分類して、上手く使っていただきました。一つの家具、一つのプロジェクトにこんなに多くの石種を使う機会は初めての経験です。また、従来の建築プロジェクトで床や壁に用いる石材は板状になっていることが多いですが、今回のベンチでは立体的な塊を使っていくような箇所があり、面的ではない石の魅力の伝え方にも可能性を感じました。

植栽とともに百貨店内に憩いの場を生む(撮影/阿野太一)
永山氏:
陶磁器片は、当初は実験で苦労をした素材でもありました。陶磁器は器の状態では、その表面に釉薬で色がつけられていますが、破片になると素材の白色が出てきます。当初は、陶磁器の柄や色を活かせるかと思っていましたが、テラゾーは、骨材の表面を研磨するため、釉薬の部分があまり残りません。しかし、その白い色合いが、大理石とは違った雪のように純粋な白さを感じさせ、また、器によって様々な形状の断面を見せてくれることが分かり、その独特の面白さを取り込めるよう工夫しながら仕上げています。
横田氏:
表面を研磨してみないと、どのような色、形になるか完全には分からないので、こちらではある程度の配置を原寸サイズであらかじめバランスを検討し、現場では石貼り付けに立ち会って指示させてもらい、後は原田左官の職人さんたちの技術とセンスで、形にしてもらいました。
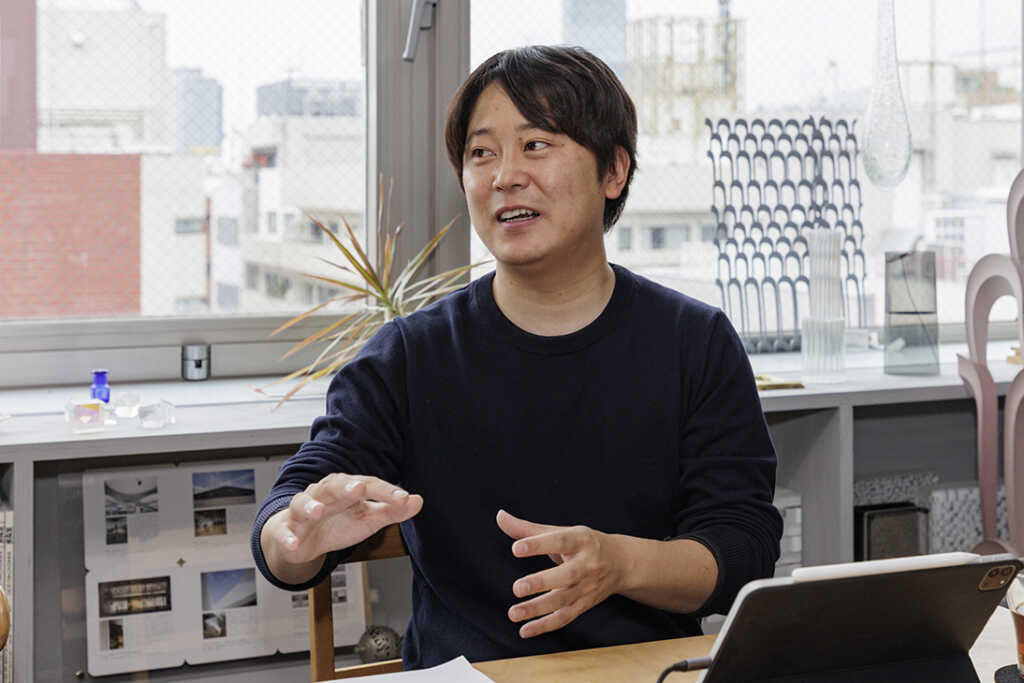
永山祐子建築設計の横田英雄氏
奥山氏:
陶磁器片の角度を調整しながら、様々な形を表出していく様子を見て、とても興味深く、もっと大きなサイズや形状のものでもチャレンジしたいという思いを持ちました。私たちのもとには大小様々な陶磁器片がありますが、その一つひとつの個性を活かしたデザイン表現を体験できたのは大きかったです。
私たちは九谷焼の世界に触れ始めてまだ日が浅いですが、窯元の工房に行くと、捨てられてしまう予定の素材や端材の中に、面白いものがたくさんあって、そんなものをもっと拾い上げていきたいという思いを持ちます。一方で、それらは面白そうな素材だけど、どう活かしたら良いか分からず見過ごされているものでもあり、そこに価値を与えてくれる永山さんのような才能ともっと積極的にコラボレーションしていきたいと思っています。

永山氏:
このベンチが置かれている空間を訪れる人の多くは、エシカルなものづくりといったストーリーではなく、最初はベンチのデザインや手触りといった、シンプルな素材感を感じ取ります。環境に配慮したものづくりはもちろん重要ですが、その手前にある、見たことのない表現への楽しさも大切だと思っていて、最終的にどんな色や形が出てくるか分からないコントロールできない部分、偶然から生まれる唯一無二のものの魅力が、有機的なベンチの形状や周りの植栽と調和し、この空間の魅力になっていると感じます。通常の製品としての建材は性質をコントロールされた素材ですが、その安定した空間の中に、意図しない驚きや発見のあるものが加わると、新しい体験が生まれる。一つひとつは小さな魅力をもった素材だけど、それらが集まって、人や商業のにぎわいや楽しさを生み出していく、そんな可能性を秘めた面白い素材、モノとの出会いを大切にしていきたいですね。
〈了〉
永山祐子/永山祐子建築設計
1975年東京生まれ。1998年~2002年青木淳建築計画事務所勤務。2002年永山祐子建築設計設立。2020年~2024年、武蔵野美術大学客員教授。2023年よりグッドデザイン賞 審査副委員長。主な仕事、「LOUIS VUITTON 大丸京都店」「豊島横尾館」「女神の森セントラルガーデン」「ドバイ国際博覧会日本館」「東急歌舞伎町タワー」、大阪・関西万博「ウーマンズ パビリオン」、パナソニックグループパビリオン「ノモの国」など。JIA新人賞(2014)、山梨県建築文化賞、東京建築賞優秀賞(2018)、照明学会照明デザイン賞最優秀賞(2021)、World Architecture Festival Highly Commended(2022)など。現在、Torch Towerなどの計画が進行中。http://www.yukonagayama.co.jp/